子どもたちの声は、小さく、繊細。
怖い、悲しい、不安といったSOS はコトバにできないこともあります。
大人にとって子どもの声を受け止めることはカンタンではないでしょう。
でも、「うまくできる」の前にはたくさんの「うまくできない」があるもの。
国連で「子どもの権利条約」が採択されて30 年あまり。
日本の子どもたちは、いまも人権を主張できずにいます。
一人ひとりの力は小さいかもしれません。
でも、たくさんの大人が力を出しあえば変化は起こせるはず。
協力しあう大人の姿は、子どもたちの励ましにもなるでしょう。
この日本で、人権を主張できない 1,500 万人を支えるために。
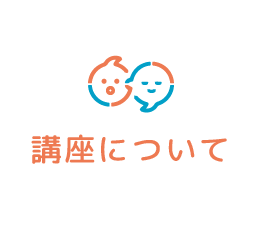
子どものアドボカシーを分かりやすくお伝えする講座や子どもの権利について理解を広げる講座を開催。子どもと関わりあう大人たちにヒントをお届けしたりともに考える場を提供したいと願っています。
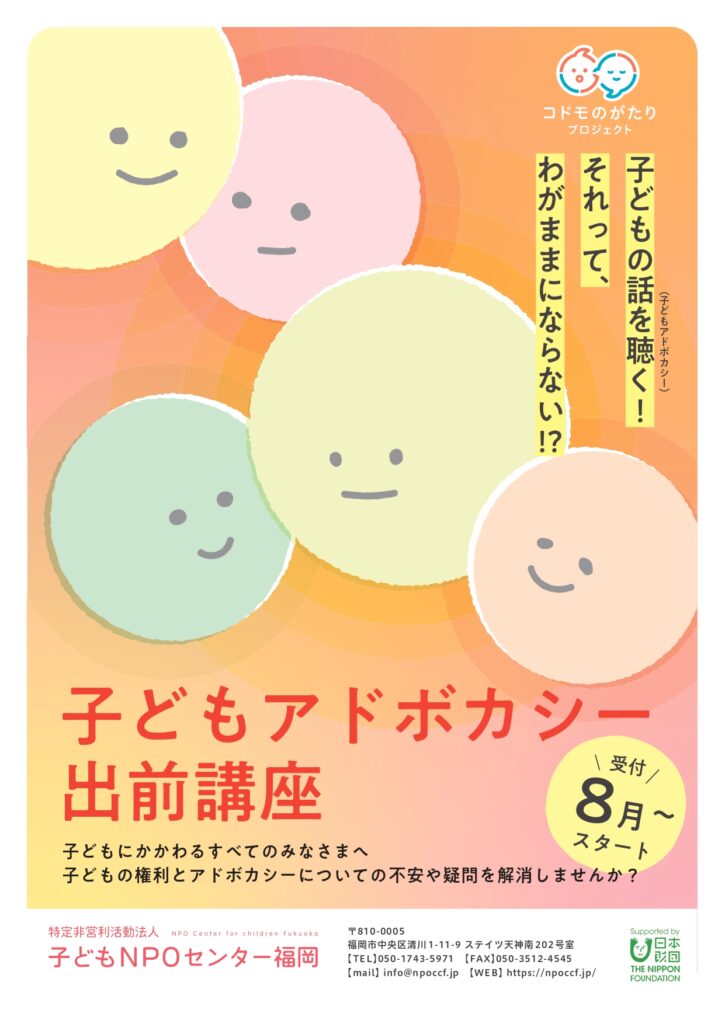
子どもアドボカシー出前講座
子どもの声を聴くのが大事と分かっちゃいるけど、
どこから始めたらいいの?と思っている方のため
に。現場に伺ってお話しします。子どもへの声かけ
や話の聴き方など、スモールステップですぐに行動
できる、実践的な講座です。

どんな課題があるの?
子どもの権利条約を批准して25年余り経つ日本ですが、「子どもの権利」の概念がおとなにも子どもにも浸透していないことで、子育てが辺縁化され、少子化が進んでいます。
さまざまな子ども政策に子どもの意見が反映されない為、権利ベースで子どもが使いやすいものになっていません。同じような施策が、バラバラの表現や手法で実施されているケースもあります。また、子どもの意見表明が活性化されていないことで、子どもの諸課題(いじめ・不登校・子ども若者の自殺・虐待等)の予防・発見・対応が非効率になっています。
そして子ども支援の方法が、科学や効果的なプログラムよりも、「愛情」や「母性」といった曖昧な要素で焦点化されることで、一部の人達の犠牲的労力を前提としたものに集約されがちになっています。
課題解決のために
子どもの権利を子どもたちがうまく安全に使えるように、おとな側の文化を作っていくことを目指します。特に子どもの「意見表明権」の活用を、子育てと子育て支援の共通認識にすることで、市民とさまざまな分野の子ども支援が効果的に協働する下地をつくります。
フォーマルアドボカシー
学校や学童、そして児童養護施設など子どもの集団に関わる現場では、子どもの意見表明権を活用することで、関りが効果的・効率的になることを、それぞれの現場で分かりやすくプレゼンテーションできる人材を養成します。
インフォーマルアドボカシー
家庭や地域では、「子どもの権利」という言葉になんとなく不安な感じがする人も多いでしょう。「子どものいう通りにしないといけないの?」「子どもがわがままになるんじゃ…」など。子どもの意見表明権を活用することは、長期的にみると、子育てや子育て支援が楽になったり、子どもを叱るストレスがなくなる等のメリットが多いのです。それらのことを分かりやすく、周囲の人たちにプレゼンテーションできる人材を養成します。
ピア・アドボカシー
権利教育、特に子ども同士でも権利行使を助け合う力があり、それはおとなによる関わりより効果的であることも多いです。発達に応じた手法で、さまざまな子どもたちに権利を使う方法を分かりやすくプレゼンテーションできる人材を養成します。
独立アドボカシー
上記に述べた3つとは異なる、利害関係のない独立した立場からアドボカシーを専門的に実践する支援提供者を養成します。福岡では、この部分を2021年に新たに設立された「子どもアドボカシーセンター福岡」が担います。
子どもの権利活性化のための人材育成や、当事者へのプレゼンテーションを科学的・構造的に作り続けることにより子どもにやさしいまちづくりが進んでいくことを目指します。
1.コドモのがたりプロジェクト広報啓発事業 1.公開シンポジウム
2.子どもアドボカシー出前講座
公開シンポジウムを通して、司法・教育・福祉のそれぞれの分野から、子どもの意見表明のための様々な取り組みを報告し、共通化への試みとトータルな議論を深めます。子どもアドボカシー活用講座では、子どもの養育現場での様々な不安に応え、独立アドボカシーを受け入れる素地を作るためのプログラムを実施します。
2.コドモのがたりプロジェクト人材育成事業 1.人材養成チーム会議
2.フォーマルアドボカシーインフルエンサー養成講座
3.インフォーマルアドボカシーインフルエンサー養成講座
4.ピアアドボカシーファシリテータ養成講座
5.思春期の子どもの意見表明(仮)
子どもアドボカシーの4つのジグソーのそれぞれのピースが機能するためのプログラムを、施設や学校、保護者に向けて実施します。また、子ども同士の互いに理解しあう力を有効に使い、信頼を独立アドボケイトへ引き継ぐための「ピアアドボカシーファシリテーター」を養成するためのプログラムを実施します。さらに、それぞれの役割をトータルでコーディネイトする役割を含めた、人材養成チーム会議を立ち上げます。
3.コドモのがたりプロジェクトプログラムデザイン事業 上記事業で使用するプログラムは、概念を伝えるだけでなく、受講する側の認知に働きかけ、具体的なスキルや行動変化に結びついていくものである必要があります。他のNPOや研究者、市民とも協力しながら、構造化されたプログラムの開発を行います。
1.学校や児童養護施設や児童相談所など全てのフォーマルな場所で子どもたちを支援する人たちに対して、子どもの権利活用のための講座が定期的に実施できる制度・人材・教材が全国に用意されること。
2.保護者や里親や子育て支援の人達が、楽に安心して子育てするために、子どもの権利活用学習の機会をいつでも持てる制度・人材・教材が全国に整うこと。
3.子どもが集団で過ごすあらゆる場所で、意見表明権を始めさまざまな権利活用の学習や、互いの権利を支え合う学習ができる制度・人材・教材が全国に整うこと。
4.市民とさまざまな分野の子ども支援の人達が子どもの権利活用の重要性と、それが意見表明権から始まることの有効性を共有出来ていること。
5.これらの活動を通して、子ども基本法の制定やこども省の設置に向けて、市民の対話が活性化され、実効性の伴うものになっていくこと。